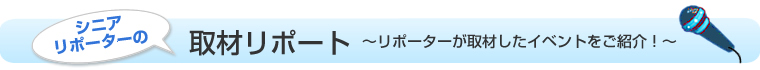- 川崎市消費者行政センターキャラクター「てるみ~にゃ」が講座入口で

- 西田教授による消費者トラブル被害者の心理について
消費者トラブルを未然に防ぐには、家族や地域の見守りが大切である。このような状況から川崎市消費者行政センターでは、もうだまされない地域で高めよう「見守り力」をテーマに2月に2回の講座(南部、北部)と3月4日にはエポック中原でフォーラムを開催した。
北部エリアの講座には高齢者だけでなく、「見守り」の関係者等約50名の参加者が熱心に受講していた。
講座の内容
一部では 実際にあった屋根の点検を事例とした寸劇で消費者トラブルの実態を再現。その後「トークディスカッション」が行われた。
トークディスカッションでは消費生活専門相談員の坂井悦子氏、片平地域包括支援センター豊島麗子氏、川崎合同法律事務所川口彩子弁護士により事例紹介が行われた。
ホームヘルパーが高齢者の「何かおかしい」に気づき消費者行政センターに連絡し被害を未然に防げた等、地域の「見守り」への取り組みが報告された。
そして、川口弁護士は騙されている事に気づかない高齢者が多いので、専門職だけではなくご近所、家族の気づきが大切である事を強調していた。
二部では 「心理学から見る消費者トラブルの手口」と題して立正大学心理学部西田公昭教授によるユーモアを交えながら、説得力のある講義があった。
大前提として、騙す・騙されるは誰もが経験している日常現象、従って誰でも騙される可能性がある事を忘れない。「騙された」に気づかない時もあるので、日頃から皆で協力し合って次の様な被害対策訓練をする事の重要性を話された。(1)過信を捨てる練習 (2)怪しさに気づく練習 (3)ストレス耐性づくり(4)はっきりと断る練習 (5)味方を探す。
最後に、詐欺対処の「さしすせそ」の話があった。さっと警戒モード、しっかり相手を確かめる、ずばっと怪しさを見抜く、せいいっぱい誘惑や恐怖に耐える、そく誰かに相談する。その中で特にずばっと怪しさを見抜く力について強調していた。怪しさとは(1)希少性の強調(2)即断即決の要請(3)優しい勧誘者(4)絶対得をする話(5)不得手な内容(6)動揺した状態(7)権威者や合意者情報の強調(8)多勢に無勢の状態である等である。
一部では地域の見守り力の大切さを、二部では消費者心理とトラブルの手口を説明した具体的でわかり易い講座であった。
*消費生活トラブルで困った時は川崎市消費者行政センターへ
相談窓口電話番号 044-200-3030
月~木曜日9時~16時・金曜日9時~19時

西田公昭教授のユーモアあふれる講義

寸劇「屋根壊れていますよ、点検しましょうか」

トークディスカッション
麻生区役所 第一会議室
片山 泰子
高齢者世帯、単身高齢者が増え、家族間、ご近所との関係が希薄になっている現在は消費者被害のみならず、地域での見守り力の大切さを痛感させられた。